コラム:カーボン全盛期が生んだ「自社設計しないブランド」、「自社生産しないブランド」の乱立、そこに依存した日本の自転車業界の低迷の脱却のきっかけはあるのか?
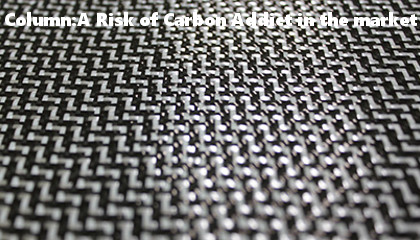
このカーボン全盛期、その弊害の一つと言えるのが「自社設計しないブランド」、「自社生産しないブランド」の乱立だ。1980年代から1990年代にかけて、MTB全盛期にはハンドメイドブランドが乱立したが、そのほとんどが自社生産にこだわったブランドだった。しかしその生産量からニーズの多さに対応できなかったり、精度が出ていないケースなどが増え、ハンドメイドブランド乱立時代は終息を迎えた。
時代が変わり生産はメーカーと製造工場という分業構造が成立し、小さなブランドは大手にOEM製造委託、さらにはカーボン全盛期となり工場が独自に作り出したカーボンフレームの中から気に入ったものを選択して名前を載せるだけの時代となった。多くのブランドが自社設計することなく製造の現場が作ったものをそのまま採用、もしくはA社の前三角とB社のリア三角を合わせてキメラを作ることでオリジナル設計・デザインと名乗るケースが増えた。製造工場依存ブランドとも言えるこうしたブランドの乱立、そしてそこへの依存が今現在の業界の低迷の一端となっているだろう。
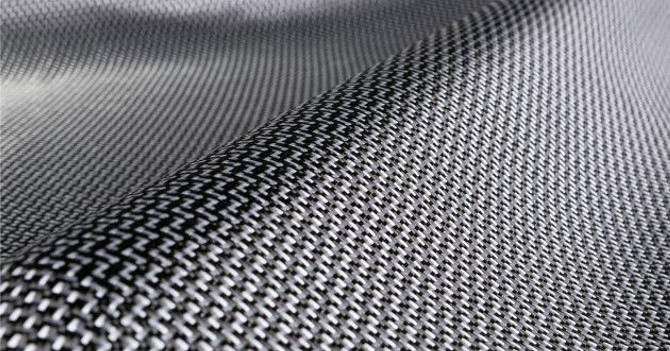 そのようになった理由の一つが量産化体制の問題だ。カーボンには型が必要となり、その金型が非常にコストがかかるのだ。その為よほど資金力のある会社でない限り、自前で金型を設計、作るところまでいかないのが現実だ。そうなれば製造工場が自前で用意したものの中から「選ぶだけ」という形式が自然と成立したのだ。メーカー側は金型を作るというリスクなく済むことが、このスタイルを大きく蔓延させた。マイナーチェンジ程度であれば金型に少し手を加えれば済むだけであり、また大手が製造を辞めたフレームモデルの金型も中古で出回ることから、それを購入して製造を委託するケースも出てきた。
そのようになった理由の一つが量産化体制の問題だ。カーボンには型が必要となり、その金型が非常にコストがかかるのだ。その為よほど資金力のある会社でない限り、自前で金型を設計、作るところまでいかないのが現実だ。そうなれば製造工場が自前で用意したものの中から「選ぶだけ」という形式が自然と成立したのだ。メーカー側は金型を作るというリスクなく済むことが、このスタイルを大きく蔓延させた。マイナーチェンジ程度であれば金型に少し手を加えれば済むだけであり、また大手が製造を辞めたフレームモデルの金型も中古で出回ることから、それを購入して製造を委託するケースも出てきた。
その為似たり寄ったりのフレームが市場に溢れ、「没個性的」なフレームが増えた。そこで次のステップで発生したのが、カラーリングで差をつけるという選択だ。さらには中国生産のフレームを本国へ持ち帰り塗装をするだけで、「メイド・イン・イタリー」などと生産地を変えて記載できてしまうという抜け道ができてしまった。ただもちろん消費者の目もだんだんと肥えてきており、メーカーのそのような小手先の誤魔化しにはよりシビアになっていった。
しかしそれでもカーボンフレームは利益率が大きい、つまりブランドとして一発当たれば大きいのだ。最初は安く上げるためにそのような既成フレームに自社ブランド名を載せるところから始め、集まった資金で自社オリジナルデザインを作る方向へとシフトしていった優良ブランドもいくつもある。しかしその半面打算的に皮算用をし、既成フレーム依存を抜け出られないブランドもまた多くあるというのが現状と言えるだろう。
その間隙を縫うように、製造を請け負ってきた中国の工場が自社ブランドを次々とスタート、まだまだ知名度は低くとも、そのハイクオリティーと独自性を前面に打ち出し徐々にのし上がってきている。このままでは遅かれ早かれ中途半端な製造工場依存ブランドが淘汰されていくだろう。
カーボン依存が進みすぎた現状、リサイクルできない非エコな素材、また経年劣化が早く、破損しやすい(メタルフレームと比べて:転倒だけで使用不可になる確率、修正・修理が利かないケースが多いという意味での)ということデメリットをようやくいくつかの既存メディアが取り上げたり、消費者が目を向けたことにより、日本での「カーボン絶対主義」は以前に比べ下火になったといえるだろう。
カーボンは利益率が高く一過性の富と流行をもたらしたが、そこにマーケットが固執しすぎたあまりに蔓延と氾濫が起き、そして説明不足が加わり、自らの首を真綿で占めるような状態となっている。海外ブランドの多くは自国内向けには金属フレームやメタルフレームなども多く販売しているが、日本ではどうしても「カーボン主流」というレッテルが邪魔をして、圧倒的に「カーボンを売りたい主義」になってしまっている。今一度、そうした一部製品に依存している現状が今後もたらす影響をきっちりと考えなければならないだろう。
海外ではカーボンフレームとはあくまでも”選択肢”であり、日本のような「絶対的」存在とはならなかったのは、自転車というものに対してマーケットと消費者が成熟しているからだろう。それにより依存体制、また製造工場依存ブランドの乱立がそこまで大きくマーケットに影を落とすことがなかったといえる。日本はまだまだレースに関してもマーケットや消費者に関しても流行り廃りに流されやすい未成熟な状態だ。自転車という文化がこれからしっかりと定着、成熟していくには何が必要なのか、それらを見極める時期に差し掛かっているだろう。
決してカーボンが「悪」なわけではない、レースなどに適している部分も多く魅力的な新素材であることには変わりはない。魅力的な素材だからと依存しすぎ、それ一辺倒に傾倒しすぎた偏りが、いかに危険とリスクを孕んでいるのかを考えなければならないのだ。未だに見かける一部ブランドやショップなどでの「カーボン絶対正義主義」は足かせ以外の何物でもないし、優良な素材であるカーボンへの冒涜でもある。
H.Moulinette
